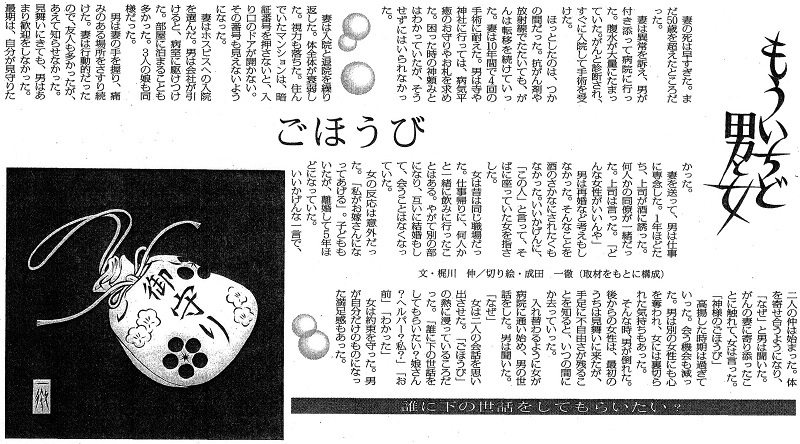もういちど男と女(16) ごほうび
妻の死は早すぎた。まだ50歳を超えてところだった。
妻は異常を訴え、男が付き添って病院に行った。腹水が大量にたまっていた。がんと診断され、すぐに入院して手術を受けた。
ほっとしたのは、束の間だった。抗がん剤や放射線でたたいても、がんは転移を続けていった。妻は10年間で4回の手術に耐えた。男は寺や神社に行っては、病気平癒のお守りやお札を求めた。困った時の神頼みとはわかっていたが、そうせずにはいられなかった。
妻は入院と退院を繰り返した。体全体が衰弱した。視力も落ちた。住んでいたマンションは、暗証番号を押さないと、入り口のドアが開かない。その番号も見えないようになった。
妻はホスピスへの入院を選んだ。男は会社が引けると、病室に駆けつけた。部屋に泊まることも多かった。3人の娘も同様だった。
男は妻の手を握り、痛みのある場所をさすり続けた。妻は行動的だったので、友人も多かったが、あえて知らせなかった。見舞いにきても、男はあまり歓迎をしなかった。最期は、自分が見守りたかった。
妻を送って、男は仕事に専念した。1年ほどたち、上司が酒に誘った。何人かの同僚が一緒だった。上司は言った。「どんな女性がいいんや」
男は再婚など考えもしなかった。そんなことを酒のさかなにされたくもなかった。いい加減に、「この人」と言って、そばに座っていた女を指差した。
女は昔は同じ職場だった。仕事帰りに、何人かと一緒に飲みに行ったことはある。やがて別の部になり、互いに結婚もして、会うことはなくなっていた。
女の反応は意外だった。「私がお嫁さんになってあげる」。子どももいたが、離婚して5年ほどになっていた。
いい加減な一言で、2人の仲は始まった。体を寄せ合うようになり、「なぜ」と男は聞いた。がんの妻に寄り添ったことに触れて、女は言った。「神様のごほうび」
高揚した時期は過ぎていった。会う機会も減った。男は別の女性にも心を奪われ、女には裏切られた気持ちもあった。
そんな時、男が倒れた。後からの女性は、最初のうちは見舞いに行ったが、手足に不自由さが残ることを知ると、いつの間にか去っていった。
入れ替わるように女が病院に通い始め、男の世話をした。男は聞いた。「なぜ」
女は2人の会話を思い出させた。「ごほうび」の熱に浸っているころだった。「誰に下の世話をしてもらいたい?娘さん?ヘルパー?私?」「お前」「わかった」
女は約束を守った。男が自分だけのものになった満足感もあった。(梶川伸)2006年7月29日に掲載されたものを再掲載2014.08.27
更新日時 2014/08/27