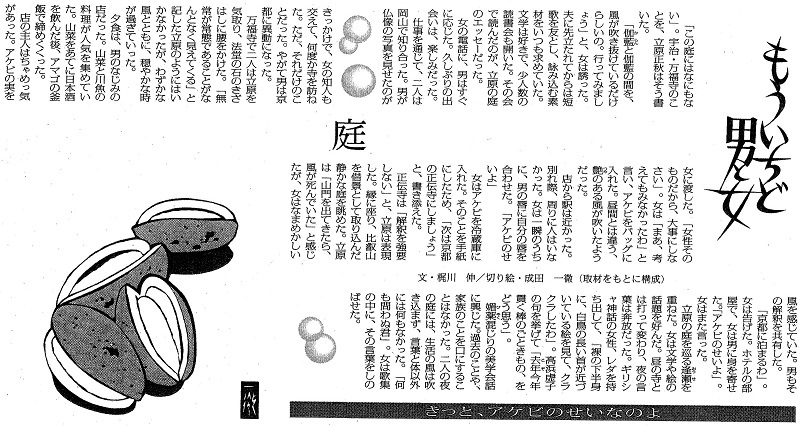もういちど男と女(12) 庭
「この庭にはなにもない」。宇治・万福寺のことを、立原正秋はそう書いた。
「伽藍(がらん)と伽藍の間を、風が吹き抜けているだけらしいの。行ってみましょう」と、女は誘った。夫に先立たれてからは短歌を友とし、詠み込む素材をいつも求めていた。文学は好きで、小人数の読書会も開いた。その会で読んだのが、立原の庭のエッセーだった。
女の電話に、男はすぐに応じた。久し振りの出会いは、楽しみだった。
仕事を通じて、2人は知り合った。男が仏像の写真を見せたのがきっかけで、女の知人も交えて、何度か寺を訪ねた。ただ、それだけのことだった。やがて男は岡山から京都に異動になった。
万福寺で2人は立原を気取り、法堂の石のきざはしに腰をかけた。「無常が常態であることがなんとなく見えてくる」と記した立原のようにはいかなかったが、わずかな風とともに、穏やかな時が過ぎていった。
夕食は、男のなじみの店だった。山菜と川魚の料理が人気を集めていた。山菜をあてに日本酒を飲んだ後、アマゴの釜飯で締めくくった。
店の主人は茶目っ気があった。アケビの実を女に渡した。「女性そのものだから、大事にしなさい」。女は「まあ、考えてもみなかったわ」と言い、アケビをバッグに入れた。昼間とは違う、艶のある風が吹いたようだった。
店から駅は近かった。別れ際、周りに人はいなかった。女は一瞬のうちに、男の唇に自分の唇を合わせた。「アケビのせいよ」
女はアケビを冷蔵庫に入れた。そのことを手紙にしたため、「次は京都の正伝寺にしましょう」と、書き添えた。
正伝寺は「解釈を強要しない」と、立原は表現した。縁に座り、比叡山を借景として取り込んだ静かな庭を眺めた。立原は「山門を出てきたら、風が死んでいた」と感じたが、女はなまめかしい風を感じていた。男もその解釈を共有した。
「京都に泊まるわ」。女は告げた。ホテルの部屋で、女は男に身を寄せた。「アケビのせいよ」。女はまた言った。
立原の庭を巡る逢瀬を重ねた。女は文学や絵の話題を好んだ。昼の寺とは打って変わり、夜の言葉は奔放だった。ギリシャ神話の女性、レダを持ち出して、「裸の下半身に、白鳥の長い首が近づいている絵を見て、クラクラしたわ」。高浜虚子の句を挙げて「去年(こぞ)今年貫く棒のごときもの、をどう思う」。
媚薬混じりの美学会話に興じた。過去のことや、家族のことを口にすることはなかった。二人の夜の庭には、生活の風は吹き込まず、言葉と体以外には何もなかった。「何も問わぬ君」。女は歌集の中に、その言葉をしのばせた。(梶川伸)2006年7月1日の毎日新聞夕刊に掲載されたものを再掲載2014.07.31
更新日時 2014/07/31